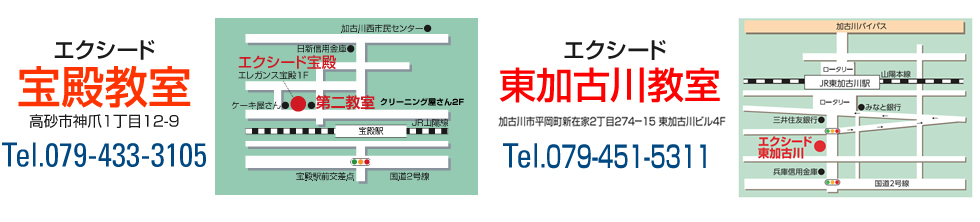オリンピック優勝投手、上野由岐子を支えた家族力
昨年の北京オリンピックで、日本ソフトボールチームは宿敵のアメリカを破り、念願の金メダルを獲得した。念願がかなった瞬間、選手たちはマウンドに集まり、その輪の中心には世界最速のスポードを誇る上野由岐子投手がいた。
彼女は準決勝のアメリカ戦、3位決定戦のオーストラリア戦とも先発完投。投球数は318球。翌日の決勝戦でも先発完投95球を投げた。この間の投球数は実に413球に及んだ。これが後に「上野の413球」と言われた。
上野由岐子は、両親と妹さんの4人家族。看護師のお母さんはすべてに厳しい母だった。母の子育ての基本は「礼儀正しく、素直な子に」「人の悪口を言ってはいけない。人に好かれる人間になって欲しい」だった。二人の娘にはいろいろなことにトライさせた。しかし、中途でやめることは決して許さなかった。例えば書道であれば、書道の最高位の段をとるまで徹底してやらせ、子どものやりぬく強さを育んでいった。いろいろな困難に直面しても自力で打ち克っていく、そんな子どもに育てようとし、そんな子どもの姿を見るのが母の喜びであった。
一方、会社員の父は、優しい父だった。両親の厳しさと優しさのバランスは絶妙だった。上野家では、両親は「仕事より家庭が第一」という考えがあり、すべて娘2人の生活スタイルに両親も合わせた。母親は、娘たちのため夜勤の多い常勤看護師をやめ、あえて非常勤のパートの看護師になった。
風呂も上野選手が高校生になるまで、家族全員で入った。風呂場では、両親に今日1日あったことを語ったり、悩みを聞いたり、ソフトボールに関する話をするなど家族団らんの場でもありコミュニケーションの場でもあった。
ソフトボールは、小学校4年生から地域の人のすすめもあり、地域のクラブに入部した。それからメキメキと頭角を現した上野選手は、5年からは男子のチームの中に入り、その中でもエースピッチャーとなった。
父はソフトとなると厳しかった。全国中学校大会の決勝戦。なかなか打てない相手投手にいらだった上野選手は、思わずヘルメットをグラウンドに投げつけて悔しさを表わした。これを見た父親は試合中にもかかわらずベンチのそばに行き、「道具にあたるとはなにごとか」と上野選手を一喝し、頭をゲンコツをくらわしたという。次打席で上野選手は、ホームランを打ち、チームは全国制覇を果たした。
高校はソフトボールの名門九州女子高校に入学して、インターハイで全国優勝を果たした。優勝して涙を流し喜ぶチームメートの中にあって、上野選手は決して泣かなかった。
彼女にはオリンピックで優勝したいという目標があったから。彼女が中2の時、ソフトボールが五輪の正式種目になり、彼女にはオリンピックで金メダルをとるという大きな目標ができた。
上野選手のはじめての挫折は、高校2年の時、体育の授業の走り高跳びで、腰の骨を折り全治3ヶ月という重傷を負った。彼女のケガを支えたのもまた家族だった。母親は片道、車で45分の道のりの病院に毎日通った。入院生活の中で、上野選手は「たいへんさ」を全くあらわすことなく、自分が強くならなければならないと思った。入院によって自分だけでなく、チームのため、家族のためという考えが芽生えたという。
金メダルが取れたのは、自分がこれまで頑張ってこられたのは、家族の力、チームのみんなの支えあってこそ。彼女はその感謝の心を一球一球にこめた。
「金メダルのためなら何回でも登板します」
上野投手の気迫のこもった投球には魂がこめられおり、これが最後のオリンピックになるという気持ちもこめられていた。それがあの「上野の413球を」生み出したのだった。
「親は子の鏡」「子は親の反映」上野家の子育てを見てつくづくそう思った。